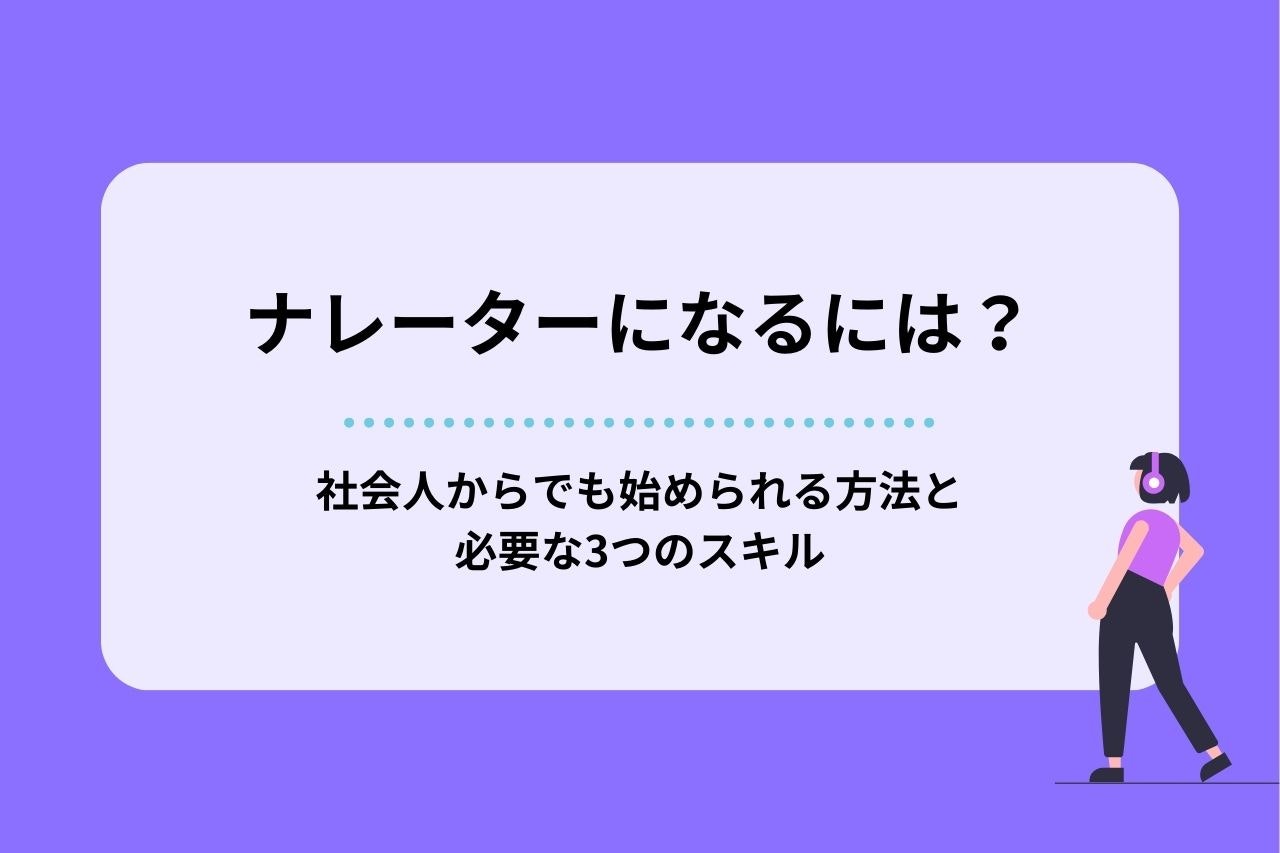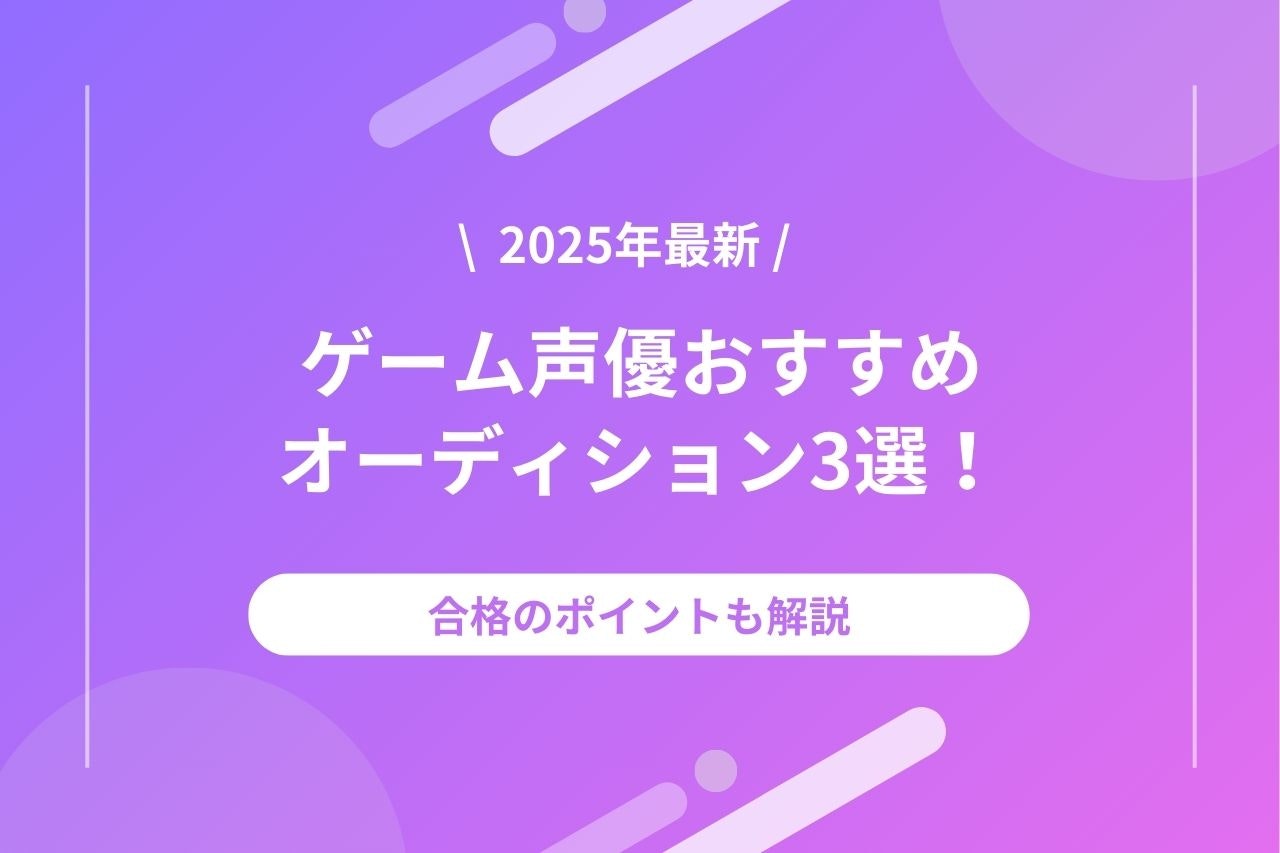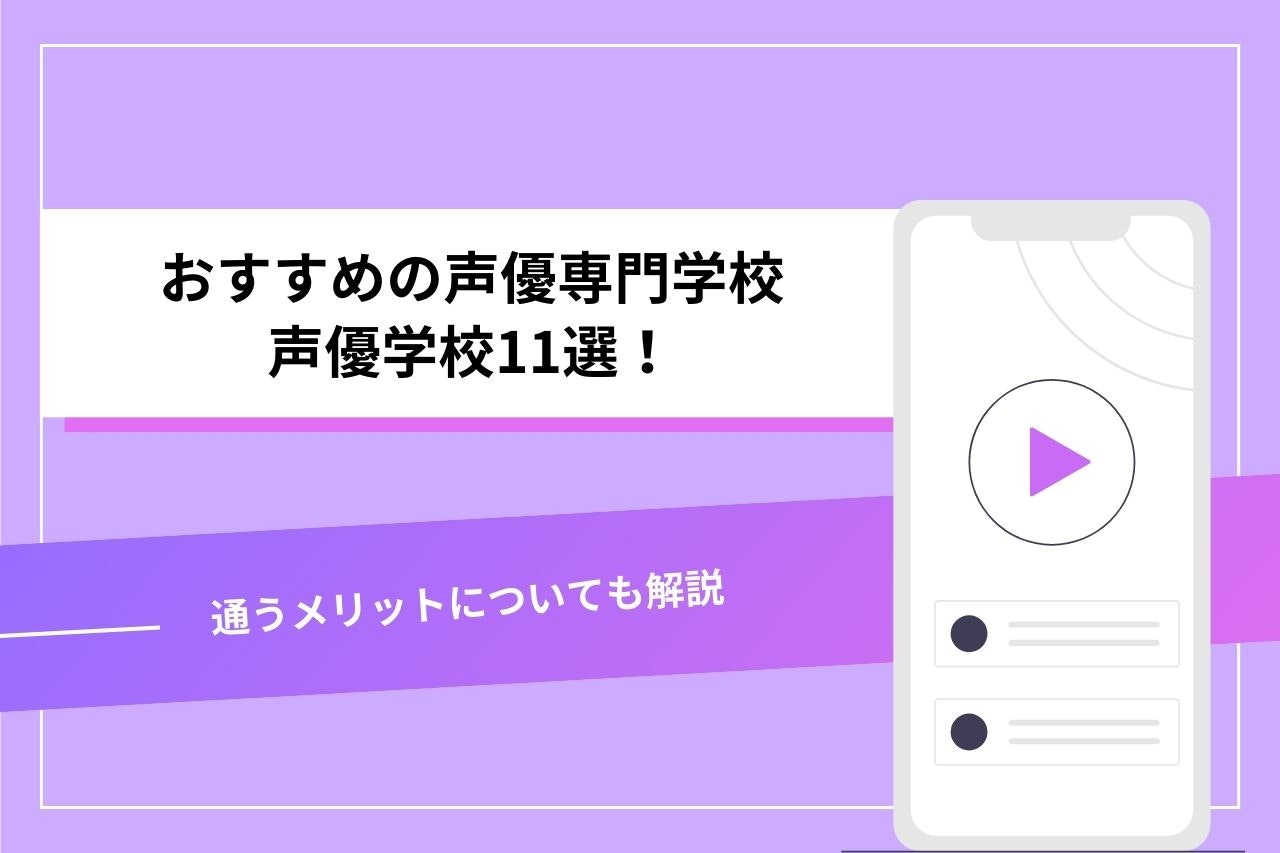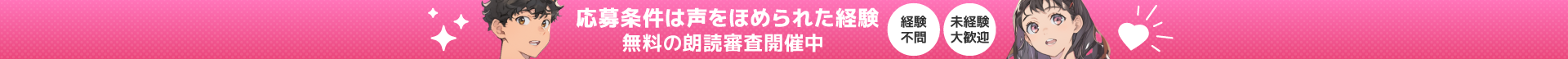
公開日:2025年04月21日
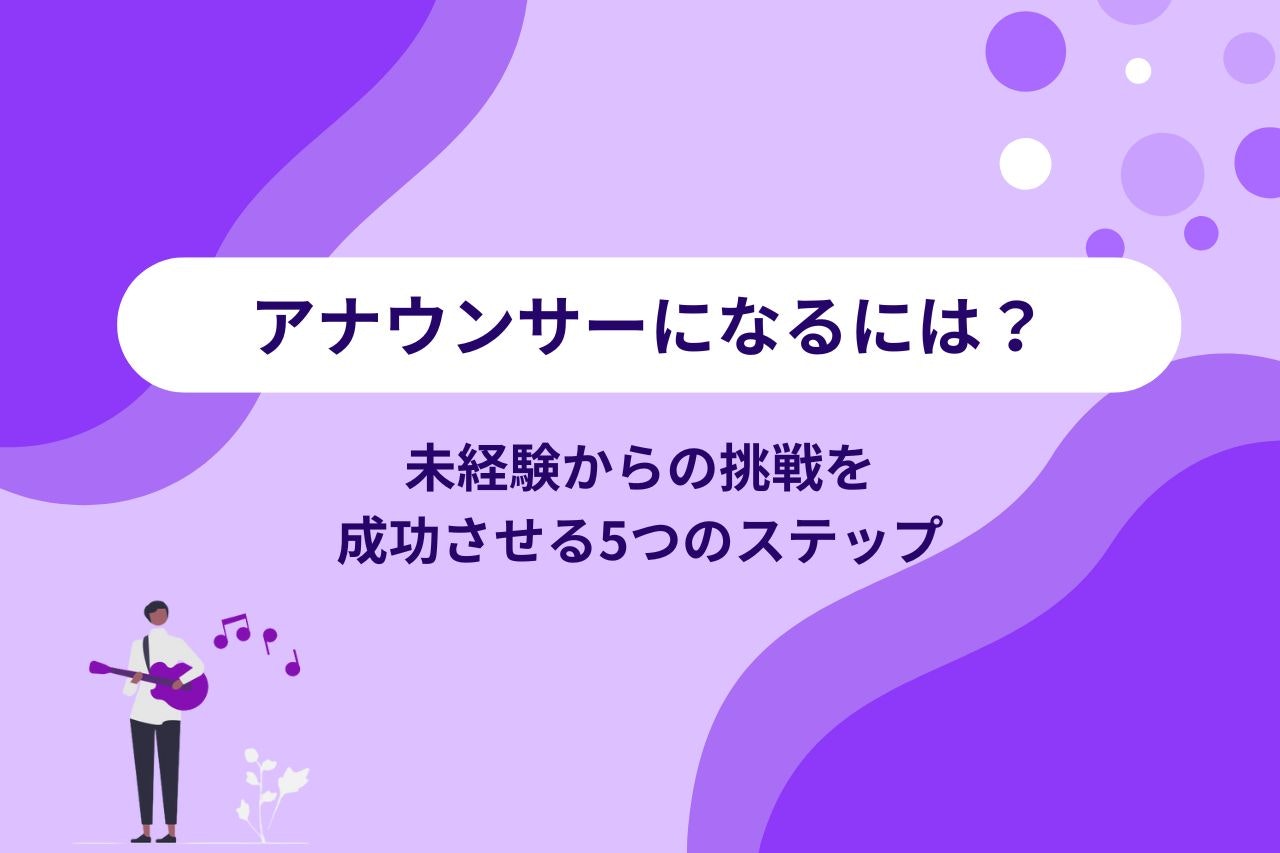
アナウンサーになるには?未経験からの挑戦を成功させる5つのステップ
声優
アナウンサーは、ニュースや情報を視聴者に伝えるだけでなく、感情や思いを届ける大切な仕事です。そんな魅力的な職業に憧れながらも「未経験でも目指せるの?」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。
アナウンサーは、正しい努力とアプローチさえあれば、誰でも挑戦できる職業です。しかし、アナウンサーになるための道のりは簡単ではありません。
そこでこの記事では、未経験からアナウンサーを目指すために実践すべき5つのステップを紹介します。アナウンサーとして必要な基本的な知識や、効果的な準備方法を分かりやすく解説していくので、夢に向かって今すぐできることを始めましょう!
1.アナウンサーになるには?
2.アナウンサーの主な仕事内容
- ニュース原稿の読み上げ
- 番組やイベントの司会進行
- 取材活動
- 実況やナレーション
3.未経験からアナウンサーを目指す5ステップ
- ステップ1. 自分の現状を把握する
- ステップ2. スキルを学べるスクールを検討する
- ステップ3. 自分でもできる練習を始める
- ステップ4. 志望するメディアをリサーチする
- ステップ5. アナウンサー試験の対策を練る
4.アナウンサー試験の流れと内容
- エントリー
- 1次面接
- カメラテスト
- 2次面接
- 3次面接
5.アナウンサーに向いている人は?必要な3つのスキル
- 1. 聞き取りやすい話し方ができる
- 2. 柔軟な対応力がある
- 3. 体力がある
6.アナウンサー試験を突破するために今すぐできる練習方法
- 腹式呼吸
- 滑舌をよくするトレーニング
7.まだ間に合う!社会人から転職したアナウンサーのエピソード
- 石川奈津紀さん
- 松下公子さん
8.アナウンサーに関するよくある質問
- 地方局とキー局で採用の違いはある?
- アナウンサー試験の倍率はどれくらい?
9.未経験からの挑戦も諦めない!アナウンサーになる第一歩を踏み出そう
アナウンサーになるには?
アナウンサーは、テレビやラジオなどのメディアを通じて情報を伝える仕事です。視聴者やリスナーにわかりやすく、正確に伝えるためには、高いコミュニケーション能力や表現力が求められます。
また、アナウンサーになるためには放送局の採用試験を受けて合格する必要があり、そのための準備も大切です。最近では、地上波だけでなくインターネットメディアやイベントの司会など、活躍できる場が広がっています。
アナウンサーになるにあたって特別な資格などは必要とされませんが、大卒者であることが一般的です。まずは基礎を学び、自分に合った方法でしっかり準備を始めましょう。
アナウンサーの主な仕事内容
アナウンサーの仕事は多岐にわたりますが、主に次のような内容が挙げられます。
- ニュース原稿の読み上げ
- 番組やイベントの司会進行
- 取材活動
- 実況やナレーション
それぞれの仕事内容について、具体的に解説します。
ニュース原稿の読み上げは、アナウンサーの最も大切な仕事の1つです。アナウンサーは、原稿に書かれた内容を正確に読み上げるだけでなく、視聴者に伝わりやすいように声のトーンやペースを調整することが求められます。
読み間違いや誤解を避けるため、事前に原稿を確認し、言葉の意味やニュアンスをしっかり理解しておくことが大切です。
さらに、緊迫感を伝える場面では、声の抑揚や強弱をうまく使い分ける技術が必要です。特に災害や緊急報道の際には、迅速かつ冷静な対応が求められます。
テレビやラジオの番組での司会進行、さらにはイベントや式典のMCを担当することもアナウンサーの仕事です。番組の進行役として、内容に沿ってスムーズに話を進め、出演者やゲストとやりとりします。
視聴者や参加者が飽きないように、テンポよく進行することが大切です。また、予期せぬトラブルが起きた際には冷静に対応し、場を取り仕切る能力も求められます。
イベントの司会進行では、参加者や観客とコミュニケーションをとりながら、会場の雰囲気を盛り上げる役割も担います。言葉をしっかり選び、タイミングよく話を進めることで、参加者や観客を楽しませる役割を果たせるでしょう。
アナウンサーの取材活動は、現場に出向き、ニュースや番組に必要な情報を集める重要な仕事です。取材では、インタビューをしたり、現場の状況を自分の目で確認したりします。
得られた情報を正確に伝えるためには、情報を整理し、視聴者にわかりやすい形でまとめるスキルが必要です。
また、現場での臨機応変な対応や、取材対象者との信頼関係の構築も大切なポイント。取材後には、得た情報をもとに原稿を作成し、ニュースや番組で効果的に伝える役割も担います。
アナウンサーの実況やナレーションは、視聴者やリスナーに臨場感を伝える重要な仕事です。実況は、視聴者がその場にいるような感覚になれるよう、スポーツやイベントの進行状況をリアルタイムで伝えます。ナレーションは、映像に合わせて情報を補足したり、物語を語ったりする仕事です。
どちらも、声の抑揚やテンションを使い分ける技術が求められます。特に実況では、状況に応じた適切な表現と、視聴者が理解しやすい言葉での説明が大切。緊迫した場面や感動的な瞬間では、感情を込めて伝える力が求められます。
未経験からアナウンサーを目指す5ステップ

アナウンサーは憧れの職業ですが、未経験から目指すためには計画的な準備と努力が必要です。以下の5つのステップで道筋を立ててみましょう。
- 1自分の現状を把握する
- 2スキルを学べるスクールを検討する
- 3自分でもできる練習を始める
- 4志望するメディアをリサーチする
- 5アナウンサー試験の対策を練る
これらの5つのステップを実践し、アナウンサーとしての道を切り開いていきましょう。
まずは、自分がアナウンサーとしての仕事に対してどれくらいのスキルを持っているのかを確認します。話す力、発音、滑舌、表現力など、アナウンサーに必要な基本的なスキルがあるか、自己評価をおこないましょう。
また、自分の強みと弱みを明確にすることも大切です。自分はどんな分野が得意な話し手なのか、例えばニュースを読み上げるのが得意なのか、司会進行のスキルを持っているのかなど、特徴を把握しておきましょう。弱点がある場合は、それを改善するための努力が必要です。
アナウンサーに必要なスキルを効率よく学ぶためには、専門的な知識や技術を提供するアナウンサースクールを検討することも大切です。アナウンサー養成スクールや放送関連の学校では、腹式呼吸や発声、発音、滑舌、ニュース読みといった、アナウンサーとして基礎から学べるカリキュラムが充実しています。
また、スクールによっては、実践的な演習や、実際の放送局やメディアなど現場での実習が含まれているところもあります。こうした実践的な体験を通じて現場でのスキルを磨けるため、実際の仕事に近い感覚で学ぶことが可能です。
スクールを選ぶ際は、講師陣の質や、カリキュラムの内容、実績なども忘れずに確認しましょう。
アナウンサーを目指すには、スクールで学ぶだけでなく、日常的に自分でも練習を重ねることが重要です。特におすすめなのが「真似をする」こと。
プロのアナウンサーの話し方やニュースの読み方を真似すると、自然な表現力や発声技術が身につきます。テレビやラジオで放送されているニュース番組やアナウンサーの番組を見たり聞いたりして、その言葉の使い方や声のトーン、話すスピードに注目しましょう。
声の抑揚や間の取り方、感情の込め方などを真似することで、実際の放送に近い感覚を養えます。真似をすることはプロの技術を効率よく習得できる方法の1つなので、積極的に取り入れてみてください。
アナウンサーを目指す際は、自分が働きたいメディアのリサーチも忘れずにおこないましょう。日テレやTBSなどのキー局、ラジオ、インターネットメディアなど、アナウンサーが活躍できる場所は多岐にわたります。
それぞれのメディアで求められるスキルや特性が異なるため、どのメディアで働きたいかを明確にし、そのメディアが求める人材像を理解することが大切です。例えば、テレビのアナウンサーは視覚的な印象や表現力が重視される一方、ラジオアナウンサーは声のトーンやトーク力が重要です。
自分がどのメディアで活躍したいのかをしっかりと決め、どのような準備が必要かを考えることが、目指す方向への第一歩となります。
アナウンサーを目指すうえで、アナウンサー試験の対策は重要かつ大きなステップです。特にキー局が実施する採用試験は非常に競争が激しく、合格するためにはしっかりと準備をする必要があります。
メディア業界や放送局が求める人材像をしっかり理解し、それに合わせた準備を進めましょう。業界の最新情報をチェックし、自分がなぜそのメディアで働きたいのか、明確に伝えられるようにしておくことが重要です。
アナウンサー試験の流れと内容
アナウンサーになるための試験は、厳しい選考になります。主な流れは以下の通りです。
- エントリー
- 1次面接
- カメラテスト
- 2次面接
- 3次面接
それぞれの選考段階で求められるスキルや適性が異なるため、事前準備をしっかり進めましょう。
まずはエントリーシートを提出します。多くの放送局では、エントリーの際に履歴書や自己PR文、オーディション用の音声サンプルなどの提出が求められます。アナウンサーになるために特別な資格や指定された学部はありませんが、応募資格として4年制大学卒の学歴が求められる場合が多いです。
エントリーシートでは、自己PRを通じて自分の強みをしっかりアピールしましょう。また、「なぜアナウンサーになりたいのか」という自分の情熱や意欲を明確に伝えることが重要です。
1次面接では、現役で活躍するアナウンサーやスタッフなどが面接官を担当する場合があります。自己紹介や志望動機のプレゼンが中心ですが、雑談形式での質問がおこなわれることも。自然な表情や明るい声での受け答えを心がけましょう。
カメラテストでは、実際に番組で使用されるカメラの前でニュース原稿の読み上げやフリートークが課されます。映像を通して表情や声、仕草がどのように映るかをチェックするためです。緊張せずに自然体で臨むことがポイントです。
2次面接では、より深い質問やケーススタディ形式の課題が出されます。各部署の責任者が面接官になる場合も多いでしょう。グループディスカッションがおこなわれたり、アドリブ力を試す質問をされたりすることも。この段階では、論理的な思考力や現場での対応力が見られます。
最終面接では、役員や幹部が参加し、応募者の最終的な適性を確認します。これまでの選考内容を踏まえたうえで、将来的なビジョンや人間性が問われ、合否が決定します。
アナウンサーに向いている人は?必要な3つのスキル

アナウンサーには、さまざまなスキルや特性が求められます。ここで紹介する3つは、特に重要なスキルです。
- 1聞き取りやすい話し方ができる
- 2柔軟な対応力がある
- 3体力がある
これらのスキルはアナウンサーとして成功するために欠かせない要素です。それぞれのスキルについて詳しく解説していきます。
アナウンサーがニュースや情報を伝える際、視聴者に正確に理解してもらうためには、言葉が明確で聞き取りやすいことが大切です。発音や滑舌をよくし、適切な声のトーンや速度で話すスキルはアナウンサーには必須。
話すスピードが速すぎると聞き取りにくく、遅すぎると内容が伝わりづらくなるため、バランスも重要です。また、言葉に抑揚をつけたり、適切な間をとったりすることで、視聴者により印象的に伝わります。
アナウンサーには、柔軟な対応力が求められます。放送中には予期しない出来事やトラブルが起こる場合も。その際に冷静に対応できる能力が重要です。
また、視聴者からの反応に適切に対応する力も大切です。視聴者の関心や感情に配慮した発言をすることで、信頼感を高め、番組や放送内容に対する安心感を与えられます。柔軟な対応力は、アナウンサーとして長期的に活躍するために欠かせないスキルです。
アナウンサーになるには、体力も重要です。長時間の生放送やリハーサル、イベントの司会など、アナウンサーは多くの時間を立ちっぱなしで過ごしたり、集中して話し続けたりすることが求められます。
放送内容によっては、緊急の対応やスケジュール変更が発生することもあるでしょう。これらの状況にしっかりと対応するためには、身体的な体力と精神的な強さが不可欠です。
健康管理や日々の体力作りも大切な部分で、アナウンサーとして長期的に活躍するためには、体力を保つことが欠かせません。
アナウンサー試験を突破するために今すぐできる練習方法
アナウンサーを目指すためには、日々の練習が欠かせません。以下の2つの練習方法を取り入れてみましょう。
- 腹式呼吸
- 滑舌をよくするトレーニング
いずれも自宅でも気軽にできる練習です。毎日の積み重ねがスキルとなって身につくため、コツコツ取り組みましょう。
腹式呼吸は、アナウンサーにとって基本中の基本です。習得することで、声が安定し、長時間の放送でも疲れにくくなります。
腹式呼吸は、胸を膨らませるのではなく、お腹を膨らませるように呼吸する方法です。以下の手順で練習しましょう。
- 1リラックスした姿勢で立つ。
- 2鼻からゆっくり息を吸い、お腹が膨らむのを感じる。
- 3口を少し開け、息を細く長く限界まで吐き出す。
腹式呼吸を日々の習慣にすることで、声が強く、安定したものになり、アナウンサーとしての基礎を固めることにつながります。
滑舌をよくするためのトレーニングも非常に重要です。どんなに重要な情報でも、言葉が伝わらなければ意味がありません。
滑舌をよくするためには、以下のトレーニングがおすすめです。
- 早口言葉:「この竹垣に 竹立てかけたのは 竹立てかけたかったから 竹立てかけたのです」などを繰り返し練習する
- 母音発声:「あ・い・う・え・お」を意識して、一音ずつ丁寧に発声する
- 滑舌の確認:発声前に鏡を見たり録音したりしてチェックする
滑舌のトレーニングは、日々の発音練習が効果を発揮します。口を大きく開けて、声をはっきりと出すことを意識して練習を続けましょう。
まだ間に合う!社会人から転職したアナウンサーのエピソード
アナウンサーを目指している方のなかには、社会人の方もいるでしょう。そこでここからは、社会人経験を経てアナウンサーに転職した方々のエピソードをご紹介します。
実際に転職してアナウンサーとして成功を収めた2人。経験を積んだ社会人ならではのスキルや知識が、アナウンサーとしての役に立つことがあるのも事実です。もしアナウンサーを目指しているなら、過去の経験が武器になるかもしれません。
石川奈津紀さんは、社会人経験を経てアナウンサーになりました。新卒でNTTに就職しましたが、NHK山形放送局のキャスターに24歳で採用。現在はフリーアナウンサーとして活躍しています。
松下公子さんも、社会人からアナウンサーに転身しました。大学時代にアナウンサーを目指して受験するものの、すべて不合格。しかし、28歳直前で地方民放局の愛媛朝日テレビに採用されました。決断力と行動力が成し遂げた結果だとご自身で振り返っています。
アナウンサーに関するよくある質問
ここでは、アナウンサーを目指している方が気になる疑問や質問をまとめました。
- 地方局とキー局で採用の違いはある?
- アナウンサー試験の倍率はどれくらい?
夢に近づくために、ぜひ参考にしてみてくださいね。
地方局とキー局では採用の違いがあります。キー局は全国的に影響力を持っているため、アナウンサー試験の倍率が高く、全国レベルで活躍できる能力が求められます。主にニュースや情報番組の進行が多く、発声やニュース読み、プレゼンテーション能力が重視されます。
一方、地方局では、地域密着型の番組制作が主な仕事であるため、地元に対する理解や親しみやすさが大切です。キー局に比べると倍率は低い傾向にありますが、地元に愛されるアナウンサーが求められるため、地域貢献の意識も重要なポイントとなります。
アナウンサー試験の倍率は非常に高いとされています。キー局の場合、応募者数は数千人にのぼり、倍率は1,000倍以上になることがあるともいわれています。地方局では倍率がやや低くなるものの、それでも高い競争率を突破しなければなりません。
そのため試験では、各局が求めるスキルや適性をしっかりとアピールすることが重要です。競争が激しいため、入念な準備と差別化が成功のカギとなります。
未経験からの挑戦も諦めない!アナウンサーになる第一歩を踏み出そう
未経験からアナウンサーを目指すのは決して簡単ではありませんが、諦めずに挑戦し続けることが大切です。まずは自分に必要なスキルや知識を理解し、計画的に準備を始めましょう。アナウンサーになるための第一歩として、声や話し方のトレーニングを積んだり、アナウンサー養成スクールで学んだりするのもおすすめ。焦らず、着実に自分を成長させていきましょう。
未経験からアナウンサーを目指すなら、Voice Planet(ボイスプラネット)もおすすめです。「声を活かした活動をしたい」という夢をカタチにする革新的なプロジェクトであるボイスプラネットは、未経験者も大歓迎!無料の朗読審査をおこなっており、声の表現活動に興味のある方を募集しています。
この審査は学生を除く20~49歳が対象で、合格後は仕事をしながらの活動も可能です。実力派プロデューサーとの面談やプロのボイストレーナーのマンツーマンレッスンなど、アナウンサーを目指している方に、必要なサポートと環境を提供します。
ボイスプラネットでアナウンサーになる夢を叶えませんか?自分の声の可能性を広げてみたい方は、ぜひ無料の朗読審査にご応募ください。